先日の11月6日、35歳になりました。
そんなタイミングで、立川市議会厚生委員会として、
岡山市(5日)・明石市(6日)・神戸市(7日)の3都市を、2泊3日で視察しました。
委員長はいわば視察の責任者でもあるので、
訪問先の選定から、現地でのご挨拶に至るまで、緊張感を持って臨みました。
(とはいえ、先方との調整や移動の手配など事務的な部分は議会事務局のご尽力あってこそ。
丁寧な企画調整に心から感謝しています。)
岡山では「在宅介護の総合特区」
「要介護になっても自宅で暮らしていけるように」という思いの元、様々な取り組みを試行錯誤しており、
また国から指定された特区として実験の場という側面もあり、岡山市での成果や結果を基に、全国的な制度や基準に発展していくという側面もあります。
最先端の介護機器の貸し出しや、「要介護になっても必要とされたい、居場所があってほしい」という思いを叶えるために有償ボランティアができるような取り組みなど、大変興味深い取り組みでした。
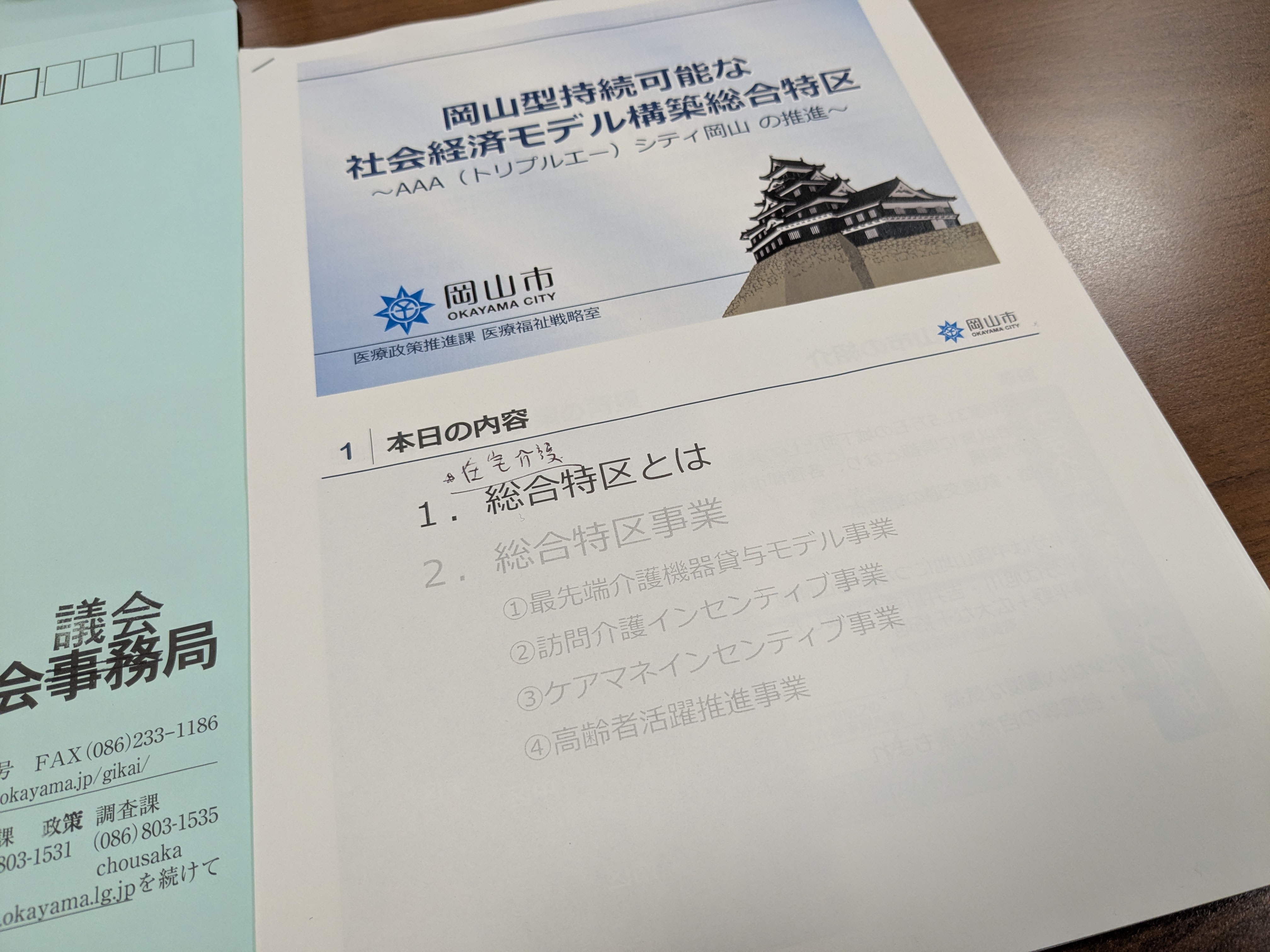
明石では「認知症への取り組み」
明石と言えば泉房穂さんが有名ですが、彼の市長時代に始まった認知症施策。
「認知症の予防やならないことを強調し過ぎると、まるで認知症になってしまったらダメだという印象を与えてしまう。
いくら予防しようと、誰もが発症する可能性がある認知症なんだから、認知症になっても安心して生きていける、
と思ってもらえるような施策体系にしたい」
そんな思いがとても人に温かく、熱のある政策とはこういうものかと痛感しました。
認知症の診断費用や、行政や福祉サービスと繋がるきっかけ作りなどを大切にしていました。

市役所前から。目の前が海で明石海峡や明石大橋も見えました。
神戸では「ヤングケアラー支援」。
2019年に市内の20代人が認知症の祖母を殺めてしまう悲しいする事件が起きたことがきっかけで全国に先駆けてヤングケアラー支援に乗り出したとのことでした。
そうしたこともあり、10代だけなく20代以降の若者のケアラーもいるという思いから、一般的なヤングケアラーではなく、
神戸市では名称を「こども・若者ケアラー」にしたとのこと。
相談窓口を設けることを始め、最初の発見者や相談者になる可能性が高い学校やケアマネ、ケースワーカーなどともしっかり連携が取れる体制がとれていました。

↑神戸市役所も海の目と鼻の先
3市とも思いと情熱が詰まっていて、地方自治の矜持とはこういうものなのだと実感しました。
視察先は委員の皆さんとも相談しながら、「どんな状態になっても、地域のなかで生きていける社会」をどう形にするか、という思いで探し、
最終的には委員長である山本が判断、手前味噌ながらとても有意義な視察だったと自負しています。
無論、上記3市と同じように簡単に立川が真似できるわけではありません。
しかし、「在宅介護」、「認知症への取り組み」、「ヤングケアラー」は、これから更に重要な課題になってくることは言うまでもありません。
今回学んだ知見を、しっかりと委員会で共有し、
立川の福祉のこれからに生かしていきたいと感じました。
視察を快くお受け入れくださった各自治体の皆さまに、心より感謝申し上げます。











